2024年12月17日に名古屋市立山吹小学校を視察しました。
第3回定例会の一般質問の中でも取り上げた、自由進度学習をとりいれている、名古屋市立山吹小学校に視察に行ってきました。5月に視察にうかがった長野の大日向小学校は日本で初めてのイエナプラン校。山吹小学校はイエナプランとして認定を受けているという訳ではありませんが、日本イエナプラン協会の協力も得ながら自由進度学習を進めてきています。公立の学校で自由進度学習を取り入れるということはどういうことなのか、私立とどんなことが違ってくるのか、その辺りを知りたいと思っていました。
まず大きな違いは、山吹小学校は異学年でクラス編成をしていないところ。通常のイエナプランでは1、2、3年生、4、5、6年生など3学年でクラスを編成し、教え合うこともねらいます。山吹小学校では学年をまたぐことなくクラスを編成していたので、学び合いという面では少し弱いかなと思いました。しかし、他の部分で異学年グループを作っての活動をするなどの工夫をしていました。異学年でクラスを編成しなかったのは、導入当初、1学年から試行的に始めたという経緯や、3学年分の授業を全て同時進行するような形にならざるを得ず負担が大きいということのようでした。
私が感じた私立と公立の大きな違いは、教員の異動があるかどうかです。私立校で特徴的な教育をする学校であれば、その教育方針に賛同した教員が集まりますし、異動もありません。公立だとそうはいかず、一斉授業しか経験したことがない先生が、異動によって自由進度学習での教え方を新たに学ばなくてはなりません。準備期間として学ぶ時間を取ることも難しそうです。そこは本当に大きな違いだなと思いました。基本的に教員の人数は一斉授業を行なっている学校と変わりません。個別に学びを進めるためには、サポート的な役割の教員もいた方が断然やりやすいはず。教員不足の中、難しいとは思いますが、複数担任制が実現できればずいぶんやりやすいだろうと思いました。また、複数の担任がいることによって、他の教員のやり方、他クラスを見ることもできるので教員どうしの学び合いも進むのではないかと思います。
導入するときにイエナプラン協会の方に来てもらって教えてもらったとのことですが、そこで大切にされていたことは、「何のために自由進度学習を導入するのか」ということ。方法論だけが一人歩きしないようにすることが重要ということだったようです。自由進度学習の“ようなもの”を進めることは、おそらくそれほど困難ではないような気がします。短時間の一斉授業をした後、繰り返し学習する必要がある、計算や漢字の練習などを個々で行うことにすれば、見た目は自由進度学習になります。しかし、自由進度学習とは、生徒が自分で考えて計画を立てたり修正する中で自分の特徴を知り、自分にあった学び方を進めながら、子ども同士もゆるやかにつながって学び合うことだと私は理解しています。方法論ばかりに注目してしまうと本来の目的が見失われるよということなのでしょう。この点はとても重要だと思いました。
公立、私立それぞれに適したやり方を考えていかないと、本来の自由進度学習の良さを発揮することができないなと思いました。とても勉強になる視察でした。


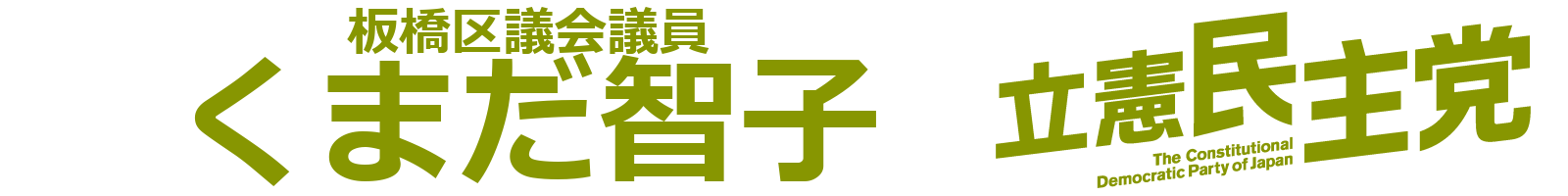







_250607_12-225x300.jpg)
_250607_26-225x300.jpg)
コメント