区議会議員になる前から私が持っていた課題意識の一つが「弱視」です。
弱視とはメガネやコンタクトレンズで矯正しても見えにくい状況を言います。
発生率は約2%、50人に1人ぐらいと言われています。小さい頃に見つけて治療につながれば、ほとんどの場合視力の発達を促すことができますが、時期を逃してしまうと見えない状態が固定されてしまいます。
さて、弱視に関しての私の問題意識は発見の方が中心だったのですが、弱視の状態にある児童や生徒さんたちは、どのような学校生活を送っているのでしょうか。板橋区には弱視の通級指導学級はありません。練馬区には通級の弱視学級が小学校1校、中学校にも1校あり、本日は練馬区立開進第三中学校に設置されている弱視学級を視察させていただきました。
まず、弱視の見え方というのはどういうものなのか。視力の程度もありますが、視野が狭い、視界の一部が見えない、視界が揺れてしまうなど、見え方はさまざまとのことでした。よく見えないと言っても状況は本当に多様なのだと理解しました。
この視察で「視野が狭い」とはどのような状態なのか体験したのですが、これほどまでに大変なのかと本当に驚きました。まず、一度に見える範囲が少ないので、文字を追うのも大変です。視線が少しずれてしまうとどこを読んでいたのかわからなくなり、探している間に車酔いのような状態になってしまいました。
教材は単に文字を大きくするだけでなく、明暗をはっきりさせる、机を斜めにできるようにするなどの工夫が見られました。片目で使う単眼鏡も複数あり、個々の生徒に合わせるだけでなく、場面に合わせても使用するとのこと。弱視の生徒が学校などでサポートが必要な際、どのようなサポートを求めるのか自分で伝える必要がありますが、具体的な伝え方なども学ぶとのことでした。
また、お話を伺って初めて知ったのですが、弱視の方はコミュニケーションに課題を持つ場合が多いのだそうです。相手の表情を読み取ることが難しいですし、視界の中央が見えない場合、話し相手と目が合わず、会話の際にそっぽを向いた状態になってしまうこともあります。周りにどのように自分の状況を開示するか、自分自身の工夫(相手と視線が合っていなくても、合っているような場所にし視線を調整するなど)も学びながらコミュニケーションについても学んでいるそうです。
指導の一つには、登校指導もあります。自宅から学校まで、実際の交通手段を使って移動できるようになるための指導です。困ったらどのように周囲に助けを求めるのかなどを実際に経験しながら学ぶので、登校指導を受けることによって、初めての場所でも行けるようになることが多くなるとのことでした。
現在、板橋区では、小学校にも中学校にも弱視学級がありません。弱視の児童生徒は盲学校に通うこともありますが、近隣の自治体同士で連携し、板橋区の児童生徒が練馬区の学校に通うことは可能です。このような情報は、弱視のお子さんを持つ保護者にしっかり届いているのだろうかという点も心配です。初めてのことばかりで本当に学びの多い視察でした。
_250607_8-1-768x1024.jpg)
_250607_17-1024x768.jpg)
_250607_12-768x1024.jpg)
_250607_14-768x1024.jpg)
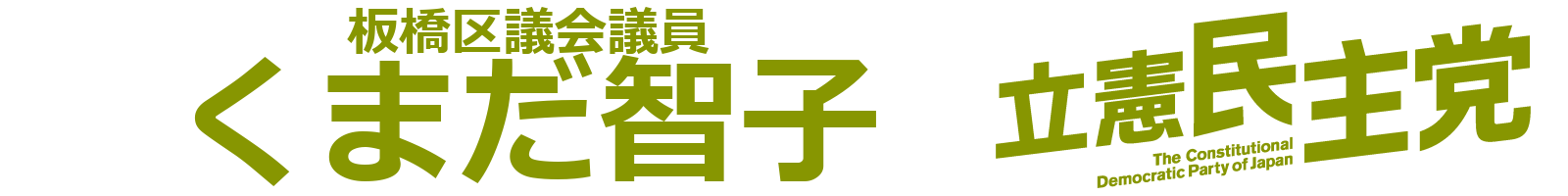

_250607_12-225x300.jpg)





_250607_26-225x300.jpg)
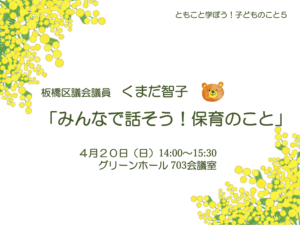
コメント