くまだ智子が、不登校支援、障がい児教育を含めた学びの場の今後について考えているところを述べます。
今年度は教育関連の様々なところに視察に行きました。また、昨年は文教児童委員会、今年度は健康福祉委員会に所属しているので、障がいのある方の学びの場についても考えることが多かったと思います。
もう何年も前からインクルーシブ教育を進めようという動きがあります。発達に課題を抱えているお子さんのいる保護者から、情緒学級を板橋にも作ってほしいという要望もいただきます。また、通常のクラスで学習がしやすいように合理的配慮にもっと理解を示してほしいという意見もいただきます。STEP UP教室に入りたいのに入れないという話も。
どれも本当にその通りなのですが、全体としてどのような形を作るのが良いのだろうか。
板橋の小中学校にはSTEP UP教室(通級)があり、学校によっては特別支援学級や、きこえとことばの教室があります。また、都立の特別支援学校もあり、フレンドセンターがあり…。
情緒学級を含め、特別支援学級はともすればインクルーシブ教育とは対立してしまいます。同じ学校内の教室であり、交流をしているとはいえ、インクルーシブと言えるかというと疑問が残ります。
今年はイエナプランの学校2校に視察に行きました。自由進度学習は合理的配慮がしやすい学び方だと思います。そもそも個別に学んでいるので「みんな」に合わせる必要がありません。実際に大日向小学校などは障がいのあるお子さんも多く見受けられました。インクルーシブ教育と一斉授業はあまり相性がよくないと思っていますので、インクルーシブ教育を進めるなら自由進度学習は必須なのではないかとも考えています。しかし一方で、自由進度学習はどうしても静かな環境をつくるのは難しい。教室数や広さに余裕がないと聴覚過敏の子などは向かないのではないかと思います。
特別支援教室、通級、特別支援学校、不登校支援、インクルーシブ教育、合理的配慮、一斉授業、自由進度学習…。どれをどう組み合わせてバランスを取るのが良いのか。最低限選択できることは大切だと思いますが、明確な答えは私の中にはまだありません。
たくさんの当事者の方の意見をお伺いし、現場を見て、考えていきたいと思います。
写真はドナルド・マクドナルドハウスを視察した際のものです。

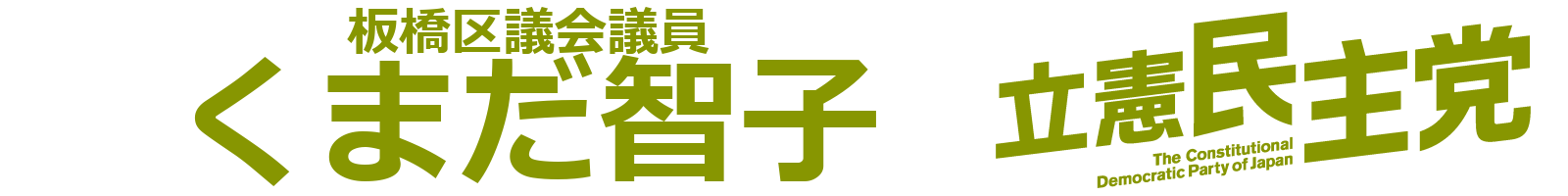



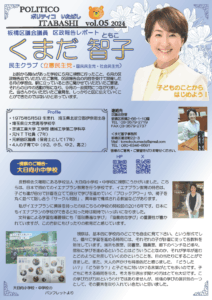

コメント